 |
千葉県銚子市 ㈲杉浦(杉浦造花店) 葬儀:葬祭:花輪:霊柩運送事業:仏壇・仏具販売 |  |
葬祭知識91件の情報項目より46-50件を表示しております
改葬(お墓の移動・引越し)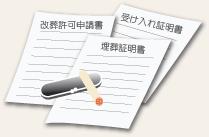 いったん埋葬したお墓を別の場所に移すことを改葬といいます。 改葬の大原則として、お墓や埋葬についての法律「墓埋法」に従わなければいけません。 改葬に関する法律上の規則や注意すべきポイントとは? ●寺院への申し出は丁寧に 改葬を行うのには、「遠方に引越しをする」、「家族の合祀墓にまとめる」、「他の宗教に改宗した」など、さまざまな理由が考えられます。 理由が何であるかによらず、墓地サイドからは望ましいことではないため、事前に理由をよく説明し理解を得ておくことが大切です。 改葬を行うことは法律上、権利として認められていますが、長年お墓を守ってくれた元の管理者には十分に礼儀を尽くしておきましょう。 お墓を改葬するときには、古いお墓から遺骨を引き上げなければいけません。 そのとき必要な儀式が「お魂抜き」です。 お墓の魂を抜いて、元の石に戻す儀式のことで読経が中心の簡素なものです。 法要のときは僧侶にお布施を包みますが、感謝の念を込めて渡しましょう。 ●改葬のための法的手続き 改葬許可証の申請には、「改葬許可申請書」「埋葬証明書」「受け入れ証明書」と印鑑が必要 改葬にはさまざまな法律的手続きが必要です。 まず、現在お墓のある市区町村の役所で「改葬許可証」を交付してもらいます。 交付を受けるには、「改葬許可申請 書」「受け入れ証明書」「埋葬証明書」が必要です。 「改葬許可申請書」は役所の窓口にあり、この書類に記入・捺印し、霊園や墓地管理者の署名・捺印をもらったものが「埋葬証明書」になります。 「受け入れ証明書」は、新しい墓地の管理者に発行してもらいます。 これらの書類3点を役 所に提出すると「改葬許可証」が交付されます。 移転先の寺院・霊園に遺骨と一緒に提出すれば、法律的な手続きはすべて完了です。 また、埋葬されている遺骨 の一部を他の墓地に移す「分骨」の場合は、市町村区への申請は必要ありません。 既存のお墓の管理者から「分骨証明書」をもらい、分骨先のお墓の管理者に提出します。 ●改葬の手順 1.新しい墓地の確保 2.受け入れ証明書の発行(新しい墓地の管理者に発行してもらう) 3.既存の墓地管理者に相談(僧侶などに事情を話し、承諾を得る) 4.改葬許可申請書の手配(現在お墓のある市区町村の役所でもらい、記入・捺印する) 5.埋葬証明書の発行(上記の改葬許可申請書に現在の墓地管理者の署名・捺印をもらう) 6.改葬許可証の交付(「受け入れ証明書」「改葬許可申請書」「埋葬証明書」を役所に提出し、発行してもらう) 7.お魂抜きの法要(現在の墓地で行う) 8.墓石の処分(新しい墓地に古い墓石を移さない場合は、無縁墓石として処分する) 9.改葬許可証の提出(新しいお墓の「お魂入れ」の法要を行う) 10.納骨法要(遺骨をお墓に埋蔵するための法要を行う) ご質問等は弊社へお問い合わせ下さい。 仏壇とは? 多くの日本人にとってお仏壇は、お位牌と共にご先祖様や亡くなった親族をお祀りし、対話をするためのものでしょう。 ですが、「仏壇」の本来の意味は、文字通り、仏像や仏具を飾り、仏様を祀る台のことです。 家庭のお仏壇は、寺院にあるお仏壇(内陣)を小型にして、厨子と一体化して箱型にしたものです。ですから、お仏壇は家の中のお寺のような存在です。 お仏壇の中央にあるくびれた台の部分は「須弥壇(しゅみだん)」と呼ばれます。 これは「須弥山」を表したもので、これより上は清浄な仏の世界、下は地上世界だと考えることもできます。 須弥壇の上には「宮殿(くうでん)」があります。その中に、ご本尊の仏像・仏画などが祀られています。 お仏壇の各所は、動植物や菩薩・天人などの彫り物や蒔絵などによって荘厳に装飾されています。これらは「浄土」、つまり汚れのない清浄な世界を表していると言われます。 お仏壇を仏様よりもご先祖様をお祀りするものと考える日本人に対して、仏教への信仰がないといって批判するのは一つの見識ですが、日本人の伝統的な宗教・習慣である先祖信仰も良いものではないでしょうか。 といっても、 お位牌がお仏壇に置かれているということは、先祖様が仏様や祖師様のお力によって浄土に導かれることを祈っている、導かれたことを信じていることを表していますので、やはり仏教なしのお仏壇は考えられないはずです。 ご質問等は弊社へお問い合わせ下さい。 初彼岸っていつ?喪明けっていつ?忌中は四十九日まで、過ぎれば忌明けとなります。 喪中は1周期までです。以後、喪明けとなります。 四十九日が過ぎて最初の彼岸を初彼岸と言います。 ですので,今年の場合,亡くなられたのが1月20日以前であれば,春の彼岸が初彼岸になります。 初盆も同じく,四十九日が過ぎて最初に迎えるお盆を初盆又は新盆と言います。 実父母が亡くなられてから,仏教では49日,神道では50日で忌明けします。 よく喪中と言いますが,これは儒教によるものです。 実父母がなくなられてから13ヶ月が喪に服する期間とされています。 数え年と同じ数え方をしますので,1月に亡くなられたのであれば,翌年の1月末までが喪中とされています。 一年ご家族さまは喪中の志で静かに過ごされるのが一般的です。 但し49日を過ぎたら ご質問等は弊社へお問い合わせ下さい。 喪中の時の新年の迎え方 初詣は控える?身内が亡くなった場合、「喪に服する」と言います。 一定期間、死を悼(いた)み、そして身を慎みます。 「忌服(きぶく)」「忌服(ふくも)」とも言います。 では新年を迎えるにあたって、どう過ごしたらよいのでしょうか?宗派や地域によっても異なってきますが、ここではごく一般的なことをお話しします。 年賀欠礼のごあいさつ喪中には年賀状は出しません。とうぜん年賀欠礼状を出されていると思います。 どこまでが範囲かは、それぞ れ立場上変わってきますのでご注意を。 年末に不幸があって、年賀欠礼が間に合わなかったり、毎年きちんと季節の挨拶をされたい方は、1月7日の松の内が過 ぎてから、寒中見舞いとして出されるとよいでしょう。 文面も「〇〇の事情で年賀欠礼させていただきました。」と言葉を添えて下さいね。 ※ちなみに浄土真宗では、死を穢(けが)れとみなす忌服の習慣を否定します。 このことから気にせずに年賀状を出すと言う考えの方も中にはいらっしゃいます。 新年の過ごし方一般的に正月飾り(鏡餅、門松、しめ縄など)やおせち料理はしません。お屠蘇でのお祝いもやりません。普段どおりに過ごします。 世間ではおめでたいお祝いムードですので、いっそう我が家では寂しくなりますが、故人の冥福をお祈りすることが大事なことです。 「あけまして、おめでとう!」新年のごあいさつはもちろんNG! つい言ってしまいそうですが、気をつけて下さい。 神社や仏閣への初詣も控えた方がよいでしょう。 お正月の墓参り喪中の初詣は慎んでも、かわりにお墓へのお参りをオススメします。新年の墓参りはいつもにもまして大切なこと。 冬場の墓地や墓石の周囲には、枯れ葉や枯れ草で汚れているかもしれません。 故人が気持ちよく新年を迎えられるように、お墓の掃除は暮れのうちにすませておきたいものです。 お参りの仕方はいつもと同じように。松を飾ることはNGですので気をつけて下さい。 ご質問等は弊社へお問い合わせ下さい。 ご遺体空輸 |
千葉県銚子市 ㈲杉浦造花店 葬儀:葬祭:花輪:霊柩運送事業:仏壇・仏具販売
〒 288-0074 千葉県銚子市橋本町1969-1
銚子駅より橋本町一丁目バス停下車0分
銚子電鉄本銚子駅下車5分
TEL 0479-22-0179 FAX 0479-22-0187


